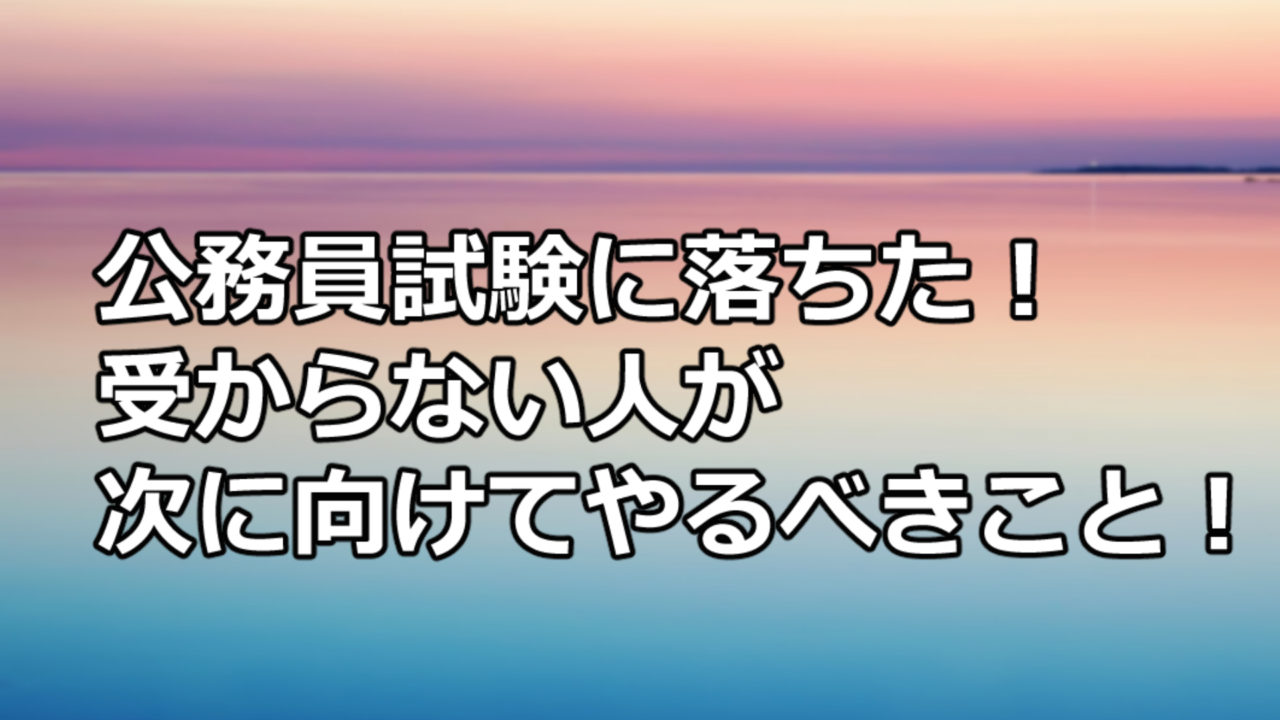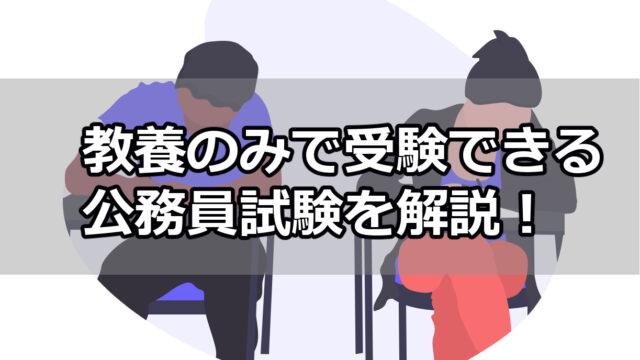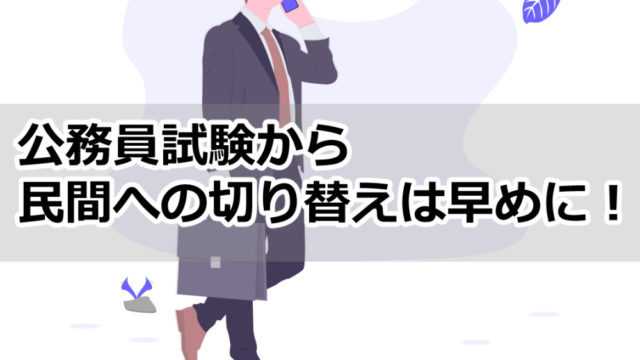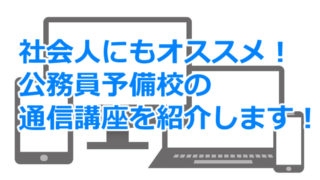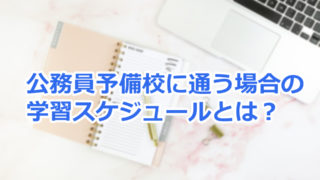「公務員試験に落ちてしまった…」
「頭が真っ白で、今は何も考えられない…」
「マジで何も考えられないので、次に向けて何をすべきか教えてほしい」
こんな極限状態の方に向けて、同じく過去に極限状態を味わった私がお答えします!
皆さんこんにちは!
ざく(@NAO85294160)と申します。
今回は今年の公務員試験に受からなかった方が、次に向けてやるべきことをお話しします。
この記事を書いている私も、過去にたくさん公務員試験に落ちています。
筆記試験で落ちたり、二次試験で落ちたり、なんなら最終面接で落ちたり・・。
何度も絶望状態を味わったことがあるので、落ちた時の何とも言えない気持ちはすごくわかります。
あの受験番号を見つけられなかった絶望感と言ったらもうね・・
次とか考えてられないですよ。何もやる気でない感じ…(/ _ ; )
でも、いつかは次に向けて動き出さないといけません。
ただ、急に気持ちを切り替える必要はありませんよ。自分のペースで徐々にエンジンを再稼働させればいいです。
そのお手伝いをするために、今回は数々の公務員試験で挫折を味わいながらも、最終的には2回も公務員になれた私が、試験に落ちてから次に何をすべきかをアドバイスさせていただきます。
さっそく結論を言うと、公務員試験に落ちた場合の選択肢としては基本的に以下の2つです。
- 公務員試験に再チャレンジする
- 民間就職に切り替える(民間就職も併願する)
では、以下で順番に解説していきますね。
本当に自分の受験番号はないのか?見逃しただけじゃないのか?って何度も合格発表画面を再確認したり…。
もしかしたら補欠に入ってるかもしれないと、現実逃避してみたり…
まぁ、色々と迷走したものだよマジで・・
いや不合格は不合格だ。
不合格者が補欠になることはないんだよ。
まぁ色々と挫折を味わってきたわけだが、いつかは自分の心を整理しつつ、次に向けて動き出さないとね。
Contents
公務員試験に落ちたら、まずは再チャレンジするか考えてみよう

まずは公務員試験に再チャレンジするかをよく考えてみましょう。
基本的に公務員試験は1年に1回しか受験のチャンスがありません。
再チャレンジすると言うことは、もう1年あなたの貴重な時間を試験対策に割くことになるわけです。
ここはよーく考えて決めましょう。
考えた結果、再チャレンジしようと決めたなら、以下のステップで再起動してくといいです。
- 自分が落ちた原因を洗い出す
- 落ちた原因に対して対策を考える
- 対策を立てつつ気分転換・リフレッシュする
順番に解説していきますね。
※この時点で、もう民間就職に切り替える意思が固まっていると言う方は下記の記事を参考にしてみてください。具体的な就活の始め方を解説しています。
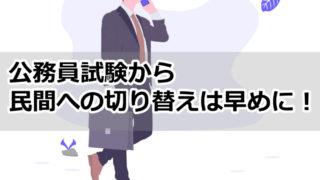
自分が落ちた原因を洗い出す
どんな公務員試験でも、まずは自分が落ちた原因を洗い出して分析しましょう。
公務員試験の内訳をざっくりみると、以下の項目になります。
- 一次試験 (筆記試験)
- 二次試験 (面接試験)
- 最終面接
原因を分析するにあたって、上記のどこで落ちたのかがポイントです。
まずは自分の受けた試験に対して、今の実力で何点得点できたのか?何位で落ちたのか?弱点は何か?
こんな感じで情報を集めてみましょう。
情報集めの一つとしては、成績の開示請求がおすすめです。
成績開示請求をしてみる
一次試験であれ、二次試験であれ不合格になってしまったら成績の開示請求をしてみてください。
成績の開示をすることで、自分の得点や順位を知ることができます。
さすがに事細かな得点の内訳を知ることはできませんが、今の実力で自分がどのポジションにいるのかを知ることができます。
ぶっちゃけこれだけで自分の弱点を知ることはできませんが、1つの分析材料にはなります。
落ちた原因に対して対策を考える
前段の落ちた原因が一次試験(筆記試験)、二次試験(面接試験や論文試験)、最終面接のどれなのか判別ができたら、その原因に対して対策を立てましょう。
一次試験(筆記試験)で落ちた場合の対策は?
落ちた原因が一次試験の筆記試験であれば、その原因は得点不足です。
ここからさらに細かく原因を洗い出すと、例えば得点不足も下記のような分類ができます。
- わからない問題があった
- 知らない問題があった
- 時間が足りなかった
他にも試験問題を持ち帰ることができる試験であれば、後から自己採点をして自分が詰まったところや正答できなかったところを洗い出してみるのもいいですね。
とにかく、それぞれの原因に対して対策を立てるためにも、得点できなかった原因を細かくグルーピングし、自分の力が不足しているポイントを見える化することが重要です。
ここで「わからない問題があった、知らない問題があった」、が主な得点不足の原因であればやはり勉強不足、演習不足と言ったことが原因です。
対策の一つとしては勉強のやり方を見直すことです。
独学で、あるいは公務員予備校で一通り勉強が終わっている方であれば、自分が苦手科目などが見えているはずです。苦手科目を克服するためにこれまでとは違った勉強法を試してみましょう。
例えば公務員予備校の単科講座を利用すれば、自分が苦手な科目だけを受講できます。
単科講座は予備校の質が高い講義を、通学するよりも安い費用で受講できるので、かなりコスパが良い対策ができます。今は通信講座に対応しているところも増えているので時間と場所も選びません。
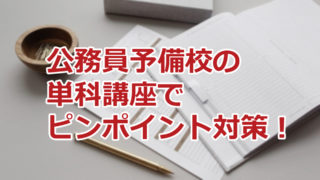
そして「時間が足りなかった」ことが主な原因であれば、常に問題を解く時間配分を意識するようにしましょう。
特に数的処理は問題も多く、時間配分が極めて大事になってきます。その分時間が取られて他の問題に手が回らないこともあります。
例えばですが、「数的処理はどんなに苦戦しても1時間経ったら次の問題に行く」と言ったマイルールを作っておくといいですね。
試験感覚に慣れるためにも、普段から1問にかける時間を意識しましょう。
ちなみに、公務員の筆記試験は大体6~7割得点できれば合格圏内だと言われていますが、実際は筆記試験の難易度によってボーダーが変わってきます。
例えば筆記試験の内容が簡単だと必然的に競争率も高くなります。
私も過去に教養試験8割と専門試験9割の得点で、落ちてしまった試験があるくらいですからね。
ボーダーは受験先や受験年度によって変わるものなので、あまり気にせずに自分の得点力向上だけを考えた方が良いです。
二次試験 (面接試験)で落ちた場合の対策は?
二次試験(面接試験)で落ちた場合、受けた公務員試験によって原因が変わってきます。
というのも、試験によってはリセット方式という採点方式を採用している場合が多いからです。
リセット方式とは?…一次試験の得点が二次試験以降で0になり(リセットされる)、考慮されない採点方式
つまりリセット方式の試験だと、どれだけ高得点で一次試験を突破しようと、二次試験以降は全員スタートラインが同じになるわけです。
筆記試験を最下位で合格した人と、トップで合格した人が同じ得点になると言うこと。
これは筆記試験を頑張った人が報われない採点方式ですよね。
個人的に公務員試験が人物重視へと変わっている典型例かなと思ってます。
筆記試験が完全に足切りのための試験になってます。
とはいえ、全ての公務員試験がリセット方式ではありません。地方公務員試験ではリセット方式がよく見られますが、国家公務員試験などは筆記試験の得点も引き継がれますね。
さて、このリセット方式だと面接試験の得点がもろに合否へと繋がることがわかると思います。
よってこの場合、落ちた原因は面接対策不足だとわかります。
面接って対策難しいですよね。筆記試験みたいに明確な正解があるわけでも無いし・・。
ただ、やはり公務員試験の面接にもある程度のノウハウというものがありまして、それを学習しているか・していないかで合否は分かれてきます。決してノー対策でクリア出来るほど甘く無いんですよね。
もし独学で面接対策が難しいと言う方は、こちらも予備校の単科講座がおすすめです。
通常、公務員予備校では受講生以外の面接対策は行ってませんし、面接対策だけのカリキュラムもありません。
しかしアガルートという公務員予備校には、誰でも受講できる面接対策の単科講座があります。
アガルートは、下記の記事でも解説していますので参考にしてみてください。
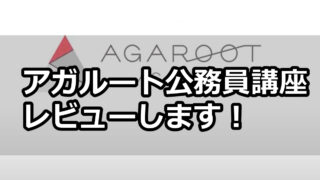
逆に、筆記試験の点数が引き継がれる場合は、筆記試験の得点力不足が原因と考えられます。
やはりこの場合も、筆記試験の対策と同じく勉強の見直しが必要になります。
例えば一次試験の筆記をパスしたとしても、点が最下位だったのなら面接で逆転することはかなり難しいからです。
ぶっちゃけ面接ってどんぐりの背比べであることがほとんどでして、よほどの事情がない限りは受験生同士それほど大差はつきません。
このように採点方式の違いで落ちた原因が違うこともあります。
最終面接で落ちた場合の対策は?
最終面接まで残った方は、その官公庁が求める合格レベルの学力、面接力が備わっていると言えるでしょう。
それゆえに最終面接に残った受験生は全員レベルが高いです。なので必然的に最終面接の難易度は高くなっています。
よって、最終面接で落ちた原因というのは他の受験生のアピール力が勝ったから…という程度にしかわかりません。
惜しくも最終面接で落ちた場合の原因は、とても分析しづらいと思います。
私なりにアドバイスできる対策としては、①その受験先には縁がなかったと割り切って別の試験を受けるか、②新しいことにチャレンジして経験を積んでから再チャレンジするの2択ですね。
②に関して、具体的に私がやったことは下記の記事でもまとめています。よろしければ参考にどうぞ。

ここで少し余談です…
「市役所試験の場合、最終面接ではその自治体に住んでいる受験生が優位になる…」
「最終面接ではコネがある受験生が優位になる…」
こんなうわさを聞いたことないでしょうか?
いわゆる受験生の住所やコネのお話です。
住所が合否に試験の合否に関係するか定かではありませんが、全く影響してないとも限りません。本当に最終面接の判断基準はブラックボックスで読めないです。
参考までに、私が最終合格した市役所の同期は住所がバラバラで、その自治体に住んでいる人もいれば、違う自治体に住んでいる人もいました。
ちなみに私自身もその自治体の住民ではなかったです。
これは住所が関係なく合格できた一例だと言えますね。
現在コネに関しては、ほとんど合否への影響は無いとみていいかと思います。
とはいえ完全に絶滅したわけじゃなくて、いまだに古いコネの慣習が残った官公庁もあるようで。あくまで個人的な意見ですが田舎の小さな町役場とかですね・・
とにかくこの辺はあまり気にしないことがポイントです。
同じ失敗を繰り返さないよう次に向けてしっかりと対策をしていこう。
対策を立てつつ気分転換・リフレッシュする
試験に落ちた原因を分析し、対策を考えたら実行に写していきます。
とはいえ、公務員試験に落ちた後のメンタルでいきなり行動に移すのは非常にきついと思います。
何度も言いますが、私も全く同じ経験をしていますので!
・・その焦燥感、憂鬱感わかります!
記念受験の方はともかく、本気受験した人であれば相当に辛いはずです。
少し休んで、気分転換をしてから少しずつでいいです。具体的に考えた対策を実行に移してきましょう
さて、ここでこれまでのポイントをまとめると
- まず、成績開示請求や試験の振り返り等で自分が落ちた原因を洗い出す。次に原因ごとに対策を考える。
- 一次試験(筆記試験)で落ちた場合の対策→根本的な勉強のやり方を見直す→公務員予備校の単科講座や通学を考えてみる。
- 二次試験(筆記試験)で落ちた場合の対策→筆記試験の得点力が十分なら面接だけでも予備校の単科講座等を利用してノウハウを身につける。筆記試験の得点力も面接も不十分ならば公務員予備校を検討するか、単科講座で必要な科目だけの対策をする。
- 最終面接で落ちた場合の対策→そもそも合格候補者レベルなので目立った欠落点はないはず→その受験先には縁がなかったと割り切って別の試験を受けるか、新しいことにチャレンジして経験を積み、過去の自分に差別化をして再チャレンジする。
最終面接で落ちる以外は、単科講座など公務員予備校を利用するという対策が最もポピュラーです。
やはり、合格者の多くは予備校の出身者が多いですからね。無難に対策するのならプロに教わるやり方が確実です。
単科講座や公務員予備校検討してみよう
公務員試験を受験したということは、一通り学習を終えられた方がほとんどかと思います。
得点力不足や面接対策不足が原因で落ちてしまった場合で、あまりお金をかけずに苦手科目だけを格安で受けれる単科講座がお勧めです。
数ある単科講座の中でも通信講座タイプなら、通学をせずに自宅で予備校の講義を受けれます。
おすすめの単科講座は下記記事で紹介していますので、参考にどうぞ。
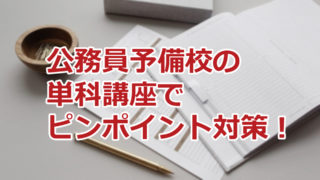
公務員予備校を利用することで公務員試験を突破するためのノウハウをたくさん学べます。
特に公務員試験を独学で勉強している方は受ける恩恵が大きいですね。
私も最初は独学スタイルで公務員試験の勉強をしてましたが、とても本番で通用するレベルには持って行けませんでした。
しかし独学を挫折し、大学の公務員試験講座を受講してから一気に筆記試験の得点力が伸びまして、翌年の公務員試験で最終合格まで辿り着きました。
やはり予備校を利用することで確実に合格までの時間を短縮できます。
おすすめの予備校は下記の記事で紹介していますので、参考にどうぞ。
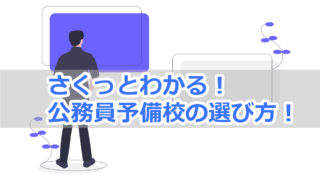
参考:違う角度からの試験対策。
ここでは参考までに、私が実際にやってみた少し違う角度からの対策をご紹介します。
具体的には以下の通りです。
- 専門試験がある試験を受けてみる
- 受験先の官公庁に直接訪問してみる
以下で解説します。
専門試験がある試験を受けてみる
教養科目だけの筆記試験で落ちてしまう場合は、専門科目がある試験を受けてみるのもいいですね。
もちろんこれは専門科目をきちんと勉強していることが前提です。
逆に専門科目があることで落ちてしまったのなら、教養科目のみの試験を受けてみましょう。
私はどちらかというと専門科目の方が得意だったので、あえて専門科目がある公務員試験を受けていました。
これにより教養科目だけの試験に比べて、筆記試験の突破率は格段に高かったです。
専門科目は勉強していないと全くわからない問題ばかりです。逆に言えば勉強をしてる人だけが得点を取りに行けます。これを利用して、専門科目をやりこんでいない受験生と差をつけるという戦略です。
受験先の官公庁に直接訪問してみる
こちらは面接対策として実際の職場を訪問してみるという方法です。
私は家族がとある政令指定都市の職員と友達だったので、アポをとって直接その方へ会いに行きました。
そのおかげで、その自治体が今力を入れていることや、リアルな職場の話、市役所の大変なところ、やりがいを感じるところ、求めている人材、回ってきた部署の話、などなど…
現場のリアルな話をガッツリ聞くことができました!
現場で働く職員から聞いた生の声は、絶対に受験先のホームページを眺めているだけでは得られない情報です。もうこの時点で他の受験生と差別化ができていると思います。
もし自分の周りに公務員の知り合いがいない場合は、学校や予備校の先生に聞いてみたり、地域などで探してみるのもいいですよ。
またこの職員を訪問したという行動を面接の時に話すことで、面接官に印象を残すことができます。
私も役所で働いてきたからわかるんですが、職場を訪問してくる受験生なんて、まぁ滅多にいませんよ。逆に言えばそういう受験生はすごく印象に残ります。
多少限定的なやり方だと思いますが、この対策のポイントはこの希少性です。
失敗は成功のもと!
以上が公務員試験に再チャレンジする場合のお話でした。
公務員試験に落ちたら、民間就活を始めてみよう(民間就職も併願する)

ここからは公務員試験に落ちた後に民間就職に切り替える、または公務員と併願をしてみるパターンのお話をします。
始めに言っておきますと、民間への就活はメリットしかありません。
これまで公務員試験対策ばかりだった方も、ぜひこれを機会に始めてみて欲しいです。
以下で民間就職のメリットをお話しします。
民間へ就職活動を始めるメリット
民間就活のメリットは以下の通りです。
- 民間から公務員というルートの選択肢が増える
- 仕事に対して世界観が広がる
- 新しい仕事との出会いにも繋がる
では、順番に解説します。
民間から公務員というルートの選択肢が増える
実は一度民間に就職することで応募できる公務員へのルートもあります。
これは社会人経験者採用枠(民間経験者採用)というもので、民間企業での職務経験や必要資格保持などの条件を満たすことで応募ができます。
近年、民間の経験や活力を行政の場に取り込みたいという風潮があるため、多くの公務員試験で社会人経験者採用枠があります。
また、公務員試験には年齢制限がありますが、社会人経験者採用枠は一般募集枠に比べて比較的受験年齢が高いのが特徴です。民間である程度経験を積んでから受験をすることが可能というわけです。
このルートは民間就職を経験したか人しか選択できないので、民間就活が生み出すメリットのだといえますね。
仕事に対して世界観が広がる
民間への就活を始めることで、世間の仕事に対する視野が広がります。
おそらく公務員を志望されている方の多くは、公務員試験一本で就活をしているでしょう。中には併願をして両立されている方もいるでしょうが、私の経験上少数派だと思います。
私は公務員になる前となった後に民間就活をやっているんですが、圧倒的に仕事の視野が広がりました。
例えば私の場合、パソコンやインターネットが好きだったので、IT業界やWeb業界を中心に転職活動をしていました。
そこでは、パソコン1台でできる時間と場所に縛られない働き方や、オフィスでストレッチしたり、音楽を聴きながら仕事をする人など、公務員の世界では考えられない職場があったわけです。
また、IT業界が提供している様々なアプリケーション・Webサービスは多くの行政課題解決に貢献していることもわかりました。
こんな感じで実際に民間就活をすると、民間しかできないこと、公務員しかできないことが明確に見えてきます。
自分の視野が広がる上に、民間業界を全く知らない他の受験生に差をつけれるなどメリットがたくさんです。
新しい仕事との出会いにもつながる
民間就活をすることで、公務員以外の新しい仕事との出会いにも繋がります。
こちらも私を例に説明すると、私は公務員受験時に公務員以外の選択肢はほとんど考えていませんでした。一応、民間ではIT・Web業界が気になっていたため、デザイン系の仕事を探してはいましたが、スキル不足を感じ半ば諦めていました。
でも、今思い返すとかなりもったいなかったと後悔しています。
この後悔もあって、公務員になった後に転職活動という形で再び民間就活を始めました。
民間就活を通して、やっぱり自分は好きなインターネットやパソコンを使った自由な働き方がしたいなぁ〜と思うようになったんです。
というのも、一度公務員を経験しているからこそ志望していたIT・Web業界と、公務員の違をリアルに感じることができ、余計にその業界へ魅力を感じたんですよね。
つまり、改めて新しくやってみたい仕事に出会えたんです。
公務員以外、眼中になかった私がですよ・・?自分でもビックリしてます。
こんな感じで民間就活は今まで自分が知らなかった、もしくは興味がある仕事に巡り合わせてくれる可能性を秘めています。
民間就活を始めるなら早いほうがいい?
さて、ここまで民間就活のメリットをお伝えしました。
「でも、就活って具体的にいつから始めれば良いの?」という疑問があると思います。
時期については結論を言うと、少しずつでもいいのでなるべく早く始めたほうがいいです。
特に新卒の方は既卒3年ルールと言って、既卒3年を超えると新卒というブランドは失われてしまいます。また、無職期間が長くなると正社員での就職が困難になるリスクもありますからね。
例えば最終面接で落ちてしまったという方であれば、ほぼ公務員試験を突破できる能力はあるでしょう。民間を併願できる余力は十分かと思います。一通り公務員試験の勉強が終わっていて、時間に余裕があるなら就活を始めてみましょう。
むしろ就活をすることで面接力やアピール力が向上するなど、公務員試験にプラスに働く可能性が高いですよ。
もちろん、気分をすぐに切り替えれない人は休んでからでも構いませんからね。
民間就活って具体的に何から始めたらいい?
次に具体的な就活の始め方・やり方ですが、実は今の就活サポートサービスはとても充実しており、とても就活を始めやすくなっています。
これは一昔前まで無かったものでして、例えば就活の流れを簡単に言うと、
- 自分で興味ある業界を探す
- 自分で興味ある企業を探す
- 自分で一から面接カードや職務経歴書を作成する
- 自分で企業にエントリーする
- 自分で面接の日程を調整する
上記のような流れになります。
これ全部一人でやると大変ですよね?
しかも公務員試験に落ちて憂鬱な状態で、いきなり初心者が準備を始めろと言っても無理があります。知識がない状態だとブラック企業へエントリーするリスクもあるかと。
ここで多くの受験生は面倒くさくなります。
実際に私もそうでした。
でも今ではこの面倒な就活を無料で全般的にサポートしてくれるサービスがたくさんあるんです。
就活初心者に一番おすすめなのは「就職エージェント」を利用することです。
就職エージェントというのは、就活生と企業をつなぐ仲介人のようなもので、あなたの就活を全面サポートしてくれます。
就職エージェントは企業側から就活生の紹介料をもらっているので、就活生は無料でサポートを受けれると言うわけです。
私も転職活動時にエージェントを利用しましたが、就活の基礎レクチャーや、私にあった企業の紹介など手厚いサポートをしてくれました。
ぶっちゃけ、相談するだけでも次に向けて何をすれば良いのか見えてきます。
少しでも民間就活を考えているなら、積極的に利用してみましょう。
おすすめ就職エージェント
- キャリアチケット
…対策後の内定率1.39倍の実績
- 第二新卒エージェントneo
…1人あたり平均8時間の手厚いサポート。
- JAIC(ジェイック)…全て正社員求人。ブラック企業を徹底除外。
また紹介さえれる求人の種類や、各就職エージェントとあなたとの相性など、それぞれ就職エージェントにも特色があります。
就職の機会や選択肢を増やすためにも、複数の就職エージェントに登録しておくと良いでしょう。
具体的な就活の始め方、やり方は下記の記事でも紹介していますので、是非参考にしてみてください。
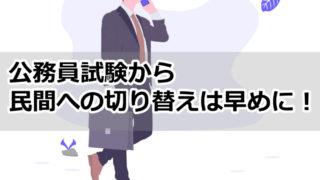
全面サポートがあるなら初心者でも始めやすいね。
しかも無料だからね。
就職エージェントはハローワークと違って、その人に合う良質な仕事を紹介してくれるのも良いポイントだよ。
まとめ

では、最後にまとめです。
まずは公務員試験に再チャレンジするかを決める。
●再チャレンジするなら以下のステップで再スタート。
- 自分が落ちた原因を洗い出す
- 落ちた原因に対して対策を考える
- 対策を立てつつ気分転換・リフレッシュ
●一次試験、二次試験、最終面接のどこで落ちたのか原因を洗い出し、それぞれに対策を立てる。
- まず、成績開示請求や試験の振り返り等で自分が落ちた原因を洗い出す。次に原因ごとに①〜③の対策を考える。
- 一次試験(筆記試験)で落ちた場合の対策→根本的な勉強のやり方を見直す→公務員予備校の単科講座や通学を考えてみる。
- 二次試験(筆記試験)で落ちた場合の対策→筆記試験の得点力が十分なら面接だけでも予備校の単科講座等を利用してノウハウを身につける。筆記試験の得点力も面接も不十分ならば公務員予備校を検討するか、単科講座で必要な科目だけの対策をする。
- 最終面接で落ちた場合の対策→そもそも合格候補者レベルなので目立った欠落点はないはず→その受験先には縁がなかったと割り切って別の試験を受けるか、新しいことにチャレンジして経験を積み、過去の自分に差別化をして再チャレンジする。
少しずつでもいいので民間就活も始めてみる。
●民間就活はメリットが多い。
- 民間から公務員というルートの選択肢が増える
- 仕事に対して世界観が広がる
- 新しい仕事との出会いにも繋がる
●民間就活のはなるべく早い時期から始めるのがポイント
- 新卒には既卒3年ルールがあり、既卒3年を超えると新卒ブランドが失われる。
- 無職期間が長くなると正社員での就職が困難になるリスクあり。
●民間就活の初心者は就職エージェントの利用がおすすめ
- キャリアチケット
…対策後の内定率1.39倍の実績
- 第二新卒エージェントneo
…1人あたり平均8時間の手厚いサポート。
- JAIC(ジェイック)…全て正社員求人。ブラック企業を徹底除外。
さて今回は「公務員試験に落ちたらどうすべきか?落ちた人がやるべきこと」をテーマにお話してきました。
何の試験にでも言えることですが、試験に落ちてしまうとつらいですよね。
今までやってきたことは無駄だったとさえ思ってしまいます。
でもそれは違っていて、今まで継続してきた積み上げは必ず自分の力になっているものです。
もし、来年公務員試験を受験するなら、その力をさらに確実にするために必ず失敗した原因の分析と対策を行いましょう。
その上で民間就活も始めれば、自分が思いもしなかった相性の良い仕事に出会えるチャンスもあります。なんなら民間企業から公務員を目指すことだってできますからね。
ぜひ自分は絶対公務員だとか、民間だとか決めつけずに、両方の世界を知った上で比較してみることをおすすめします。
自分のペースで構わないです。少しずつモチベーションを回復し、次に向かって行動していきましょう。
未来はすでに走り出していますからね。
乗り遅れないように、できることからしっかりと対策を積み上げていくことが大事です!
なぜ昨日の模試は点数が悪かったんだろう?
ずっとゲームしてたから?
いや、違うよね…