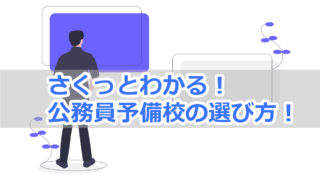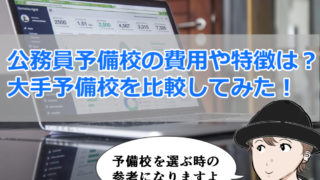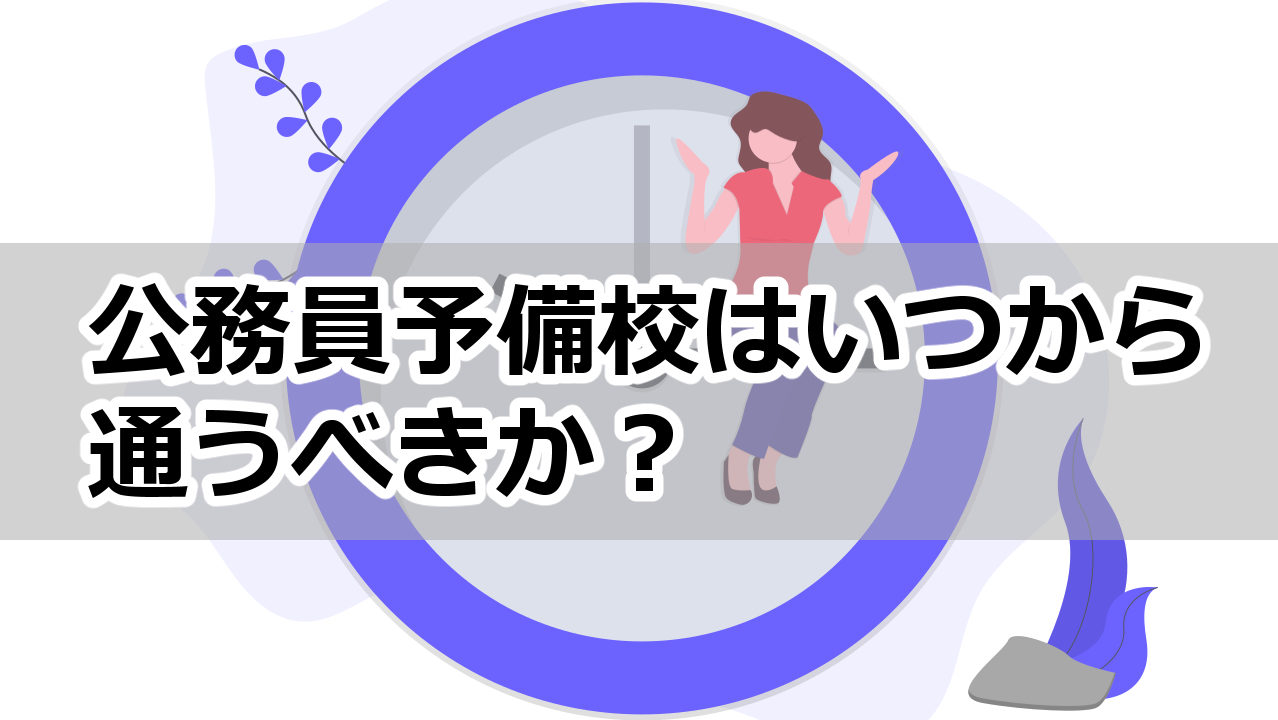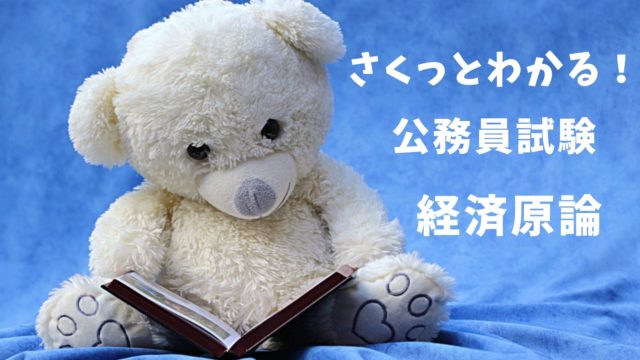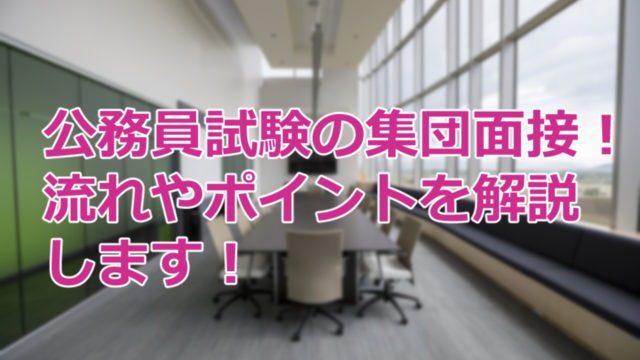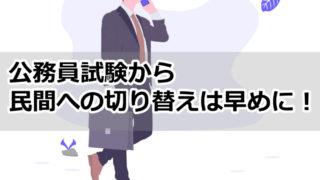「公務員予備校って、いつから通い始めたらいいの?」
「早ければ早いほどいいのかな?何か目安みたいなのがあれば知っておきたい。」
こんな疑問に答えます!
皆さんこんにちは!
ざく(@NAO85294160)と申します。
今回は「公務員予備校はいつから通うべきか?」というテーマの記事です。
本記事では
- 予備校はいつから通うのがベストか?その”目安”を解説します。
- 予備校は早めに通い始めた方がいいのか?私の経験から考察します。
- 参考までに、私自身がいつから予備校を利用し始めのたかをお話しします。
公務員試験対策として予備校を検討している方の参考になれば幸いです。
今回の記事で自分にとってベストな通学時期を見極めましょう。
Contents
公務員予備校はいつから通うのがベストか?

結論を言えばベストな通学時期というのは人によって違ってきます。
しかし、それでは話が終わってしまいますね …(^_^;)
というわけで、予備校に通い始める時期の「目安」についてより具体的に解説します。
予備校に通う時期は、受験する試験日程から逆算して考えるのがベスト!
自分が受験する公務員試験の日程から逆算して、約1年間の勉強期間が確保できる時期から通い始めるといいでしょう。
まず、公務員試験の年間スケジュールというのはだいたい決まっているので、受験する試験さえ決めれば簡単に逆算できます。
一般行政(事務)系試験の1次試験日程
- 国家総合職 (大卒程度) → 4月28日 (日)
- 国家一般職 → 6月16日(日)
- 国家専門職 → 6月9日 (日)
- 地方上級 (政令指定都市、府県) → 6月23日 (日)
※令和元年度
市役所(政令都市以外)の1次試験日程
- A日程…概ね6月第4週の日曜日
- B日程…概ね7月第4週の日曜日
- C日程…概ね9月第3週の日曜日
- D日程…概ね10月第3週の日曜日
上記のように1次試験だけ見ても、半年以上は何かしらの公務員試験が実施されています。
日程は毎年ほぼ一緒なので、1発目に受験する1次試験日を基準にして1年以上の勉強期間が確保できるようにしてみましょう。
参考までに、大手公務員予備校LECのQ&Aによれば一般的な勉強期間は以下のとおりになっています。
- 国家総合職レベル→10~15ヶ月
- 地方上級・国家一般職レベル→7~12ヶ月
- 教養試験のみの市役所や警察官・消防官レベル→4~10ヶ月、
- 高卒公務員→4~10ヶ月
上記のように国家総合職を除けば、だいたい1年程度で必要な勉強期間を確保できるということがわかりますね。つまり予備校に通う時期というのは、試験日の1年前というのが平均的にベストだというわけです。
こんな感じで、実際は受験する公務員試験のタイプによっても勉強時間は違ってきます。
なので予備校に通う時期を考えるなら、まず自分がどの試験を受験するかを大まかに決めておきましょう。
ちなみに公務員試験というのは併願するのが基本です。
併願というのは、「試験日程が被らなければいくつでも受験して構わないよ」ということです。
大まかな公務員受験の流れ
1年間しっかり試験勉強する
↓
年間に実施される公務員試験の内、日程が被らない試験をたくさん受験する
↓
筆記試験を突破したものから2次試験対策に移行
ほとんどの公務員受験生は上記のようなルートを辿ります。
例えば国家総合職など時期が早い試験は4月から実施されます。
よって、ざっくりですが具体的に予備校に通い始める時期を示すなら、
・国家総合職など4月に実施される公務員試験を受験予定なら→4月試験日の1年前から予備校に通う
・国家総合職など4月に実施される公務員試験は受験しない→5月試験日の1年前から予備校に通う
といった感じになりますね。
少し補足をすると、この1年という勉強期間は「予備校の講義の時間+1日4~5時間くらいの自学自習時間」を想定しています。
勉強期間を短く見積もればその分1日の勉強時間も多くなります。
最終的にはご自身の確保できる1日の勉強時間とすり合わせて判断してみましょう。
試験によって勉強期間が違うのは、試験科目が違うからです
前段でお伝えしたように、受験する試験日程から勉強期間を逆算すれば予備校に通う時期は決められます。
ところで試験によって一般的な勉強期間が10~15ヶ月、4~10ヶ月のように開きがありますよね?これは主に試験科目の違いが関係しています。
公務員の筆記試験は教養と専門という2タイプの科目があって、試験の種類によって教養だけの試験もあれば、教養+専門が課される試験もあります。
教養科目は高校時代の大学入試の時に受験するセンター試験に近いイメージです。
専門科目は大学の法学部、経済学部、商学部などで履修する法律系、経済系の科目です。
簡単に言うと教養だけの試験なら半年程度の勉強期間でOK。教養+専門の試験なら1年程度は確保しましょう…ということですね。
試験の科目数が多いほど、また試験の難易度が高いほど必要な勉強期間も増えてきます。
逆に言えば、
高校時代のセンター試験が今でもバッチリできる!
大学時代に専門科目の講義を履修している!
こういった状況によっても勉強期間には違いが出てきます。
以下で詳しく解説します。
教養科目のみの試験しか受けない場合
教養科目のみの試験しか受けない場合、高校時代の受験勉強(センター試験や大学入試)をどれくらいやったか?、どれくらい覚えているか?…によって勉強期間が違ってきます。
もし大学受験の現役時と変わらないレベルの学力があれば、教養科目を突破できる力はあるはずです。(教養科目は国数英社理なので、センター試験と似ています)
ノー対策とはいかないかもしれませんが、おそらく短期間で本番に挑めるレベルまで持って行けます。
人による話ですが、参考書や過去問を買ってみて独学でもいけそうと思えるのであれば、予備校を利用せずとも筆記試験の突破は可能でしょう。
専門科目(法律系や経済系)がある試験も受ける場合
専門科目がある試験を受験する場合は、大学で勉強していた人でも余裕を持った勉強期間を確保しましょう。
ぶっちゃけ公務員試験の専門科目は、大学で学習したものとは別物と思っていいくらいです。大学だけの勉強で過信するのは危険ですね。
私を例にあげると、大学時代は経済学部だったので経済学の予備知識はあったし、大学の試験でもそこそこの成績は残していました。
とはいえ、大学の講義で学習する経済学と公務員試験で出題される経済学ではポイントが違うので、対策なしでの受験は無理ゲーでした。
わりと忘れていた部分も多かったので、結構な時間を経済学の勉強に費やしましたね。
このように法律や経済などを大学時代に勉強していた人でも、専門科目の勉強は避けて通れません。一定の勉強期間を確保しましょう。
予備校はできるだけ早くから通った方がいい?

続いて予備校に通うのは早ければ早い方がいいのか?という疑問についてお話しします。
私の経験から結論を言えば、遅すぎてもいけないし、早すぎても効果薄いという感じです。
具体的な理由としては以下の通りです。
- 試験の種類にもよるが勉強期間は平均的に1年あればOK
- 2次試験の面接で話すためのネタ作り時間が必要
- 公務員になった後のことまで考えると勉強だけやるのは微妙…
試験の種類にもよるが勉強期間は平均的に1年あればOK
冒頭の「公務員予備校はいつから通うのがベストか?」でもお話ししたように、予備校は平均的に試験日から逆算して1年ほど期間を確保し、しっかりと勉強すれば1次試験突破に必要な力は十分身に付きます。
なので大学生であれば、せっかくのキャンパスライフを削ってまで、極端に早い時期から予備校に通う必要ないです。
私が見てきた限りだと、大学3年生から受験に本腰を入れる学生が多かったですね。
特に大学1~2年時は単位の取得など、学業もそれなりに忙しいと思うので、ある程度卒業までのメドがたって時間に余裕が出てくる大学3年くらいが丁度いい感じです。
逆に大学4年生から卒業までに公務員を決めたいとなると、受験できる試験も限られます。遅すぎても選択肢が狭くなってしまうので注意しましょう。
2次試験の面接で話すためのネタ作り時間が必要
公務員試験は筆記試験だけでなく面接試験もあります。面接で話すネタを用意しておくため、勉強以外にもできるだけ色んな事をやっておいた方がいいです。
例えば私の場合だと大学時代アルバイトを3年程やっていて、面接カードにも情報として書いていました。(ちなみに私は大学4年生から公務員講座を受け始めました)
他にも大学で勉強した経済学のことや、ゼミでの活動、卒論など、大学時代に経験できたことは全て面接試験のネタとして使えました。こういう学生時代の経験いうのは面接でもよく質問されます。
確かにの勉強期間を長くすれば、筆記試験の突破率は上がるでしょう。しかし近年の公務員試験は全体的に2次試験を重視する傾向にあります。
試験の種類にもよりますが、1次試験はいわゆる足切り入試のような扱いが多いですね。
つまり筆記試験でどれだけいい点をとっても公務員になれるわけじゃないので、しっかりと2次試験対策を意識した、面接の時に話せる経験値を積んでおいた方が後々有利です。
もちろん予備校でもクラスメイトや講師の方など交流する機会に恵まれているので、その中で貴重な体験は生まれるかもしれません。
でも面接で使うネタとして予備校でどれだけ本気で勉強したか、というのはあんまり使える内容じゃないです。
基本的に公務員試験で勉強を頑張るのは当たり前だと思われているし、たとえ勉強のやり込みをアピールしても、面接官も他の受験生とあなたを差別化できないんですね。
あまり早い時期から予備校に通うよりも、自分にしか語れないエピソードを持つための経験を積みましょう。
公務員になった後のことまで考えると勉強だけやるのは微妙…
前段と少し被りますが、公務員になった後のことを考えると早くから予備校で勉強づけの生活になるよりも、早くから他人と協調する社会的経験を積んだ方がいいでしょう。
民間企業に限らず公務員もチームをとして仕事をしていくことが多いので、ソロプレイで勉強ばかりしていると、公務員になってからがしんどいです。
最近の面接試験は個別面接だけでなく、集団面接、集団討論、グループワークなど複数の受験生と協力して課題に取り組んでいくタイプが増えています。
これは実際の公務員という現場で、他者と協力する能力やコミュニケーション能力というのが重宝されているからです。
予備校に通うと基本的に1日が予備校のカリキュラムに合わせる形になってしまい、時間の使い方が制限されがちです。
なので、できれば大学1~2年の内にアルバイトでもボランティアでも何でもいいので、他人と一緒に行動するような新しいことに挑戦してみることをオススメします。
他者との協調性やコミュニケーション能力というのは、面接試験でも採用後も大きな武器になりますよ。
私が予備校を利用し始めた時期について

さてここからは、私(ざく)がいつから公務員予備校を利用したか?というお話をします。
私は大学4年生の4月に大学内の学内公務員講座を受講していました。
(正確には予備校というより、予備校の講師が大学で行う公務員講座です)
ここまでの流れから言うとかなり遅めですね(^_^;)
なので在学中の公務員合格は間に合わず、卒業してから翌年の公務員試験を受験しました。
最初に受験したのは当時5月に実施されていた国立大学法人の試験です(国立大学法人の試験は現在7月に実施されています)
つまり私が予備校を利用し始めたのも約1年前からです。
私が独学を挫折し予備校の講座を受けるまで
私が公務員を目指し始めたのは、ちょうど大学3年生の時です。
何となく公務員になろうと思い、独学で公務員試験の勉強をしていました。
勉強していたと言っても公務員試験の全体像や方向性もわからないまま、とりあえず書店で買った過去問(しかも数的推理1冊)を一人でやみくもに解いていただけでした。
そして、ほどなく挫折するんですね…(^_^;)コレハムリダ
それから公務員を半ばあきらめつつ民間企業の就活を始めますが、まぁ…これもことごとく全滅しました。
このままではだめだと思い、大学4年生の4月から学内で開催されていた公務員講座の受講を始めます。この学内公務員講座というのが予備校の講師陣による出張講座だったわけですね。ここから約1年間公務員試験の勉強を全力でやりました。
私は「日本の大統領って誰だっけ?」とか言ってしまうくらいのレベルだったので、マジで1日10時間くらい勉強しました。
その結果、地方上級、国家一般職、国家専門職、市役所などの1次試験を全て突破することができました。(国家総合職は受験していません)
週3回の講義でも合格できた
私が受講していた学内講座というのは、予備校のように1週間ぎっちりスケジュールが詰まっているわけではありません。
学内講座はだいたい週3回くらいの講義で、講義時間も夕方18時から4~5時間くらいでした。
振り返ってみれば講義時間よりも自身の勉強時間の方が多かったですね。
よって、少なくとも週3回講義+1年間の勉強期間で筆記試験の突破は狙えます。
これが2~3年前から予備校に通っていたら、まず勉強のモチベーションが続いていなかったと思います。
何年もダラダラ勉強するのではなく、自分で目標やリミットを設けて集中して1年間やる方が圧倒的にパフォーマンスを発揮できますよ。
自分が受験する試験や、「いつまでに何をする」と言った期限を設ければ、逆算で予備校に通うタイミングも見えてきます。
まとめ
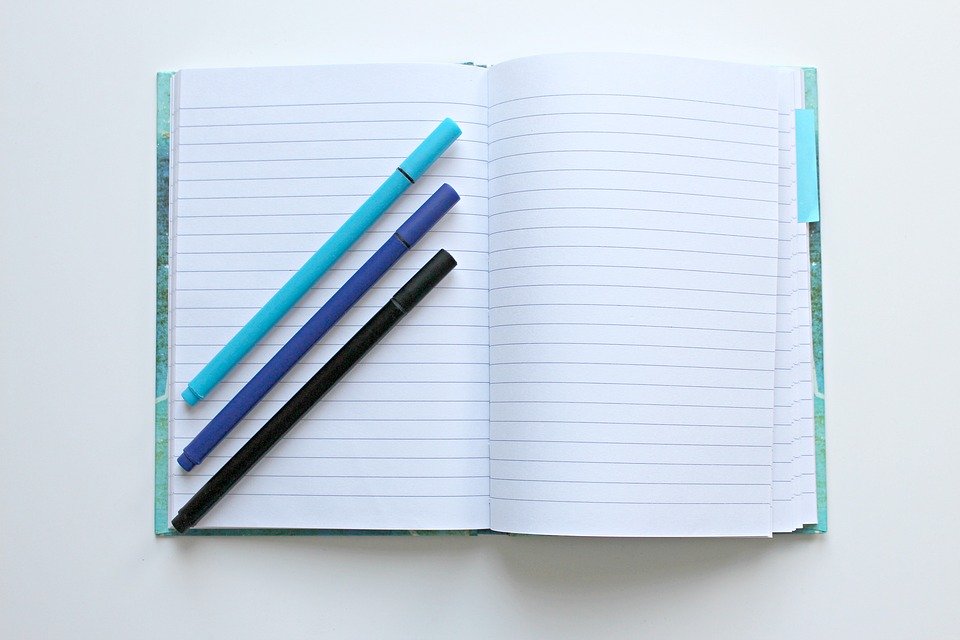
さて、今回は「公務員予備校はいつから通うべきか?」というテーマで解説してきました。
最後にここまでの内容をまとめておきます。
- 予備校に通う時期は、試験日の約1年前というのが平均的にベストなタイミング
- 予備校に通う時期は早すぎても、遅すぎても効果が薄い
- 私(ざく)自身も約1年前から週3回の予備校講座で公務員に合格しているので、経験から言っても1年間で公務員合格は目指せる
冒頭でも言いましたが、予備校に通う時期というのは最終的に人によるところが大きいです。
ぜひご自身の状況と今回の内容を照らし合わせて、最適な時期を見つけてみてください。
それでは今回は以上となります。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!
※公務員予備校の選び方や費用は下記の記事で紹介しています