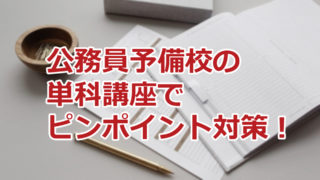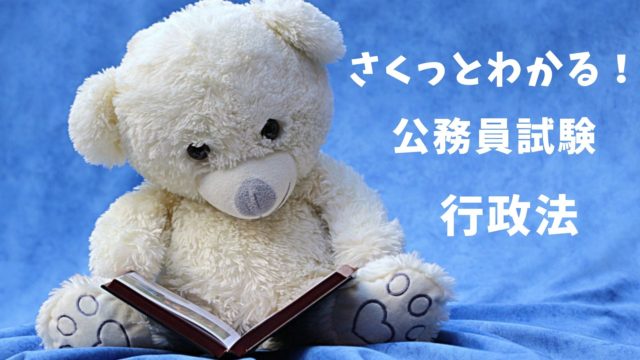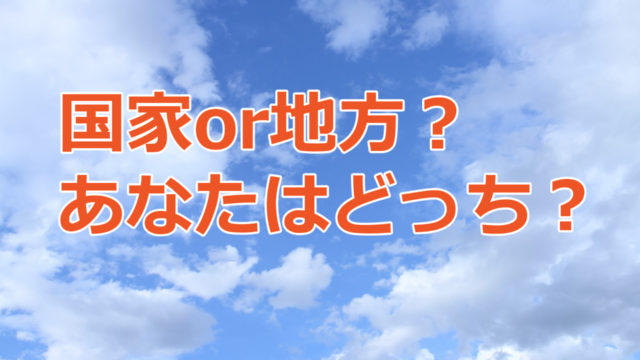公務員試験で1点でも多く得点したい!
コツがあるなら教えて欲しい!
こんな疑問に答えます!
公務員の筆記試験を受験されている方に多い悩み
「時間が足りなくなる!」
「本番だと思ったように問題が解けない!」
「なかなか点数があがらない!」
こんな悩みを解決できるかと思います。
この記事では少しでも得点を上げるために効果的な、公務員試験で意識すべき3つのコツを紹介します。
劇的に得点を上げるものではないですが、意識するだけで確実にレベルアップができます。
1点が合否を分ける公務員試験です。
ぜひコツを身につけて1点でも多く得点しましょう。
ちゃんと問題全部を見れたのかな?
10分もかかってしまった!
おかげで、得意な文書理解を解く時間があまりなかったよ~
それだと筆記試験の突破は厳しいぞ。
これを機に、きちんと公務員試験のコツを押さえておこうか。
コツその1:公務員試験は問題を解く時間配分を意識しよう

まず1つ目のコツは、時間配分を意識することです。
普段から1問にかける時間を決めて、時間を図りながら問題を解くクセをつけましょう。徹底的に1問を解く時間感覚を身につけます。
これすごく大事ですよ!
例えば、数的処理が苦手な方は1問に10分以上かかってしまうこともあるでしょう。
そうなると、残りの問題を解く時間が無くなってきます。
これだと全体の点数を結果的に1問以上下げてしまいますね。
たった1問のせいで、残りの解ける問題まで落としてしまうのは非常にもったいないです。
- 何が不得意で時間がかかるのか?
- 逆に何が得意で時間を巻けるのか?
上記を感覚的に身につけると、公務員試験は見方が変わります。
時間感覚を身につけるためには、普段の学習で時間を意識することに加え、実際に模擬試験を受験して感覚を掴むしかないです。
公務員試験はいかに1問を解く時間を早くするかというのがポイントなんですが、過去問とばかり向き合っていると、この時間を意識する感覚が身に付きにくいんですよね。
この点、模擬試験は今の実力を確認しつつ、時間を気にしながら本番演習ができる非常に有意義なものです。
過去問ばかり解いていても、なかなか時間を意識しないし、身についた力を確認することが難しいです
制限時間のある本番形式の模擬試験でシュミレーションをしておくと、時間感覚を身に着けることができるし、時間のかかる自分の弱点を洗い出すこともできます。
これぞ模擬試験を受けるメリットですね。
時間感覚を早めに身につけておくと、本番試験でも安定した結果をだすことができます。
模擬試験は予備校ではもちろん、産経公務員模擬テストなどの、自宅で受験できる全国レベルの公開模擬試験も実施されていますので、まだ試験スタイルを経験したことのない方は是非受けてみましょう。
コツその2:公務員試験は問題を解く順番を意識しよう
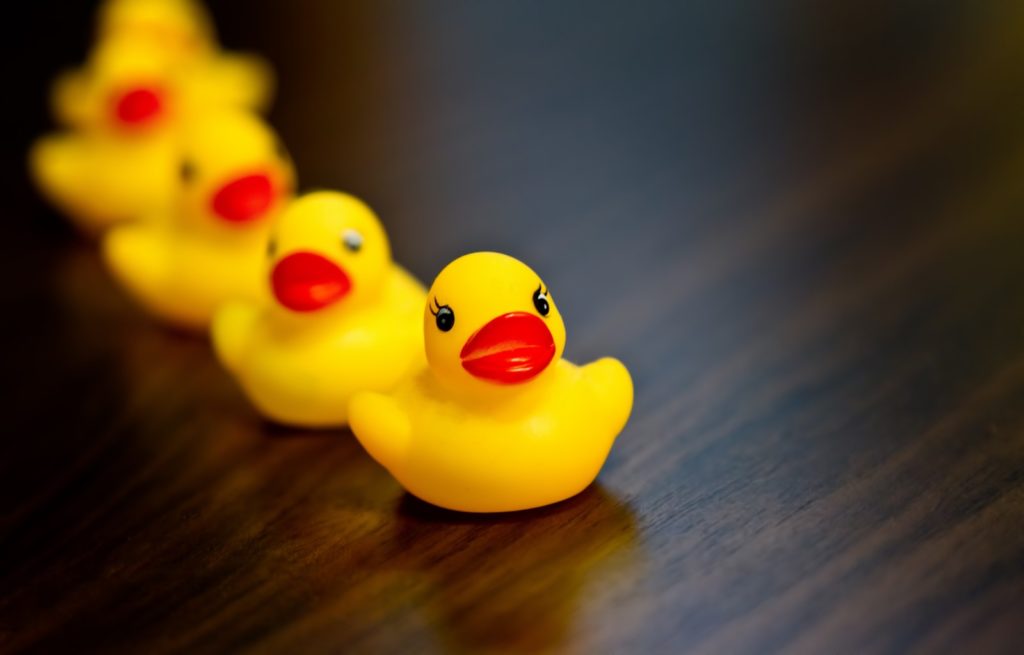
2つ目のコツは、問題を解く順番を意識することです。
実は問題を解く順番を意識することで、点数を上げることが可能です。
では具体的にどのような順番を意識すれば良いかというと
解けるところから優先して解いてく!
当たり前ですが、この順番が大事です。
公務員試験は素直に1問目から解いていく必要は一切ありません。自分が得意な問題、わかる問題をガシガシ解いていきましょう!
これは、コツ1で紹介した時間配分にも影響することです。
基本的に公務員試験は取捨選択なんですよ。
わからない問題や、知らない問題に5分〜10分と時間をかける必要はありません。
というかそんなヒマないです。
よく言われますが、公務員の筆記試験は満点をとる試験ではないです。
おおざっぱに言うと、約6割~7割程度の得点をとれれば合格圏内だと言われています。
極端なこと言うと、解ける問題から順番に解いて6〜7割くらい正解していれば、残りは解かなくても合格できるわけです。
自分が得意な、わかる問題から攻めていきましょう。
ここからは参考までに私の問題を解く順番をお伝えします。
私の場合、最初に数的処理から解いていました。
数的処理に1時間と時間を決めており、どんなに途中でも、1時間で次の問題に移るようにしていましたね。もちろん数的処理の中でも解ける問題から先に解くのが鉄則です。
果てしなくどうでもいい情報ですが、私は嫌いな食べ物は先に食べて、好物を最後に残しておく派の人間です( ˘ω˘ )
当初、数的処理を最後に解くようにしていたのですが、せっかく順調に問題を解いていても、「でも最後に数的残ってるのかぁ~」という思いが常にあっていつも後味悪く教養試験を終えていました。
これを先に嫌いな数的処理から片づけるスタイルにしたところ、後味すっきりな状態で教養試験を終えることができ、次の専門試験もモチベが上がった状態で取り組めるようになりました。
そして、全体的な点数が上がるという結果に繋ぐことができたのです。
「なんだか時間が足りない」、「思ったように点数を上げれない」という方は、問題を解く順番を改善してみましょう。
コツその3:公務員試験は捨て科目をつくろう
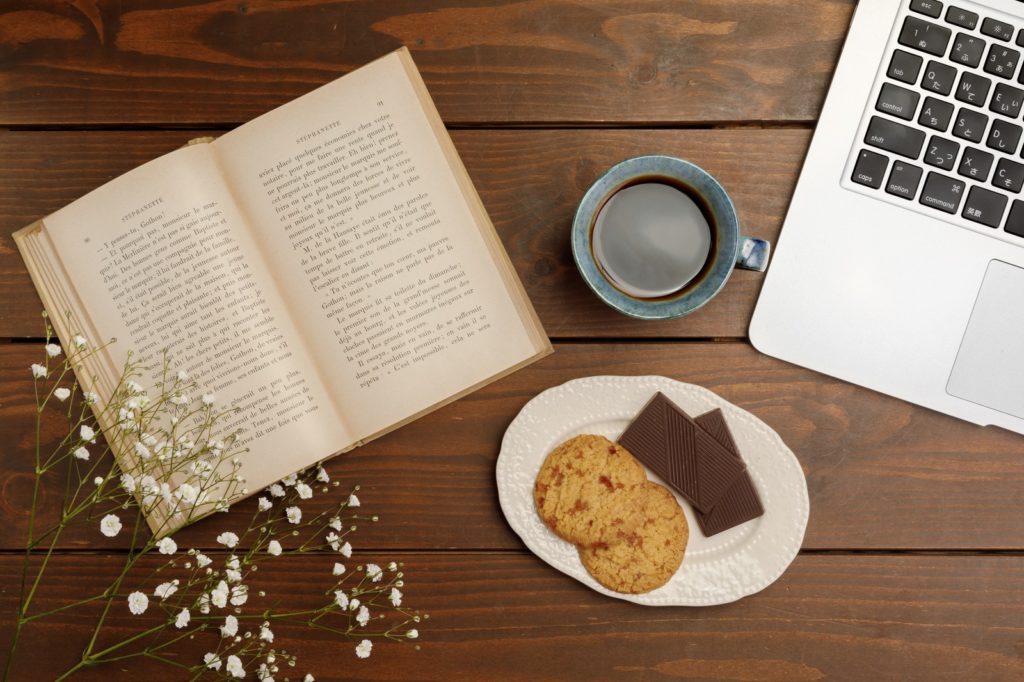
コツの3つ目は捨て科目を作ることです。
捨て科目を作ることで、勉強の効率化をはかり得点アップにつなげます。
以下でもう少し具体的に説明します。
前文で設問単位で取捨選択をしようと言いましたが、捨て科目を作るとは、
科目単位でも取捨選択をする!
と言うことです。
公務員試験の科目はとても多いです。
全科目を全て網羅的に勉強するとなると、大変な時間がかかります。
試験本番までの時間は限りがあります。時間は有効に使わなければなりません。
やらなくてもいい科目は極力やらないというのも、筆記試験で得点をアップさせるためのコツなんですよね。
とはいえ、捨て科目を作るのはなんだか不安だ…という方もいると思いますが、
多くの筆記試験を突破してきた私も捨て科目を作っているので、安心してもらって大丈夫です。
じゃあ、どの科目を捨て科目にすれば良いのか?というお話ですが、目安としては、自分が不得意かつ出題数が少ない科目という感じですね。筆記試験の合否に与えるダメージが少ない科目といったところです。
よって、どの科目を捨て科目にするかは人によって違うということになります。
参考までに私が捨て科目にしたもの、その理由を以下で紹介します。
教養試験で捨てた科目
- 数学(1問だけなので捨て)
- 物理(1問だけなので捨て)
- 思想(特に対策せず)
- 文化芸術(特に対策せず)
専門試験で捨てた科目
- 経営学(地方上級試験で2問でるが、時間なかったので捨て)
- 社会学(中級試験で一度試験科目にあったので少しかじる、それ以外では使わないので基本捨て科目)
- 会計学(国税で必須科目だが、会計原則しかやらなかった。ほぼ捨て科目状態だが、筆記試験は2回受けて2回とも突破
これはあくまで参考です。本当に捨て科目は人によって違いますからね。
理系の方なら、数学、物理を捨てるのはあり得ないという方もいるでしょう。
専門試験では、複雑な刑法を捨てたり、暗記が多い国際関係を捨てる方もいらっしゃいます。
ここはぜひ自分にとって優先順位の低い科目を洗い出してみてください。
ちなみに、捨て科目を作ると言うのは、あくまで自分の学習時間をより重要な科目にあてるための手段ということです。
なんでもかんでも捨て科目にするのは危険なので、他の科目でカバーできる範囲で捨て科目を作りましょう。
※下記の記事で捨て科目についてまとめていますので、参考にどうぞ。

まとめ

・模擬試験を受けるなどして、1問にかける時間の感覚をつかもう
・問題を解くベストな時間配分を決めよう
・取捨選択して、解ける問題から順番に、優先的に解こう
・無理せず捨て科目を作り、勉強時間を効率的に使おう
分かる問題から解いていったら、ちゃんと問題全部を見れたよ。
分からない問題とばしたら、結果的に点数も前より上がった!
公務員試験は取捨選択だ。難しい1問を時間かけて解くより、解ける問題を落とさないことが大事だよ。
これも後回し!あ、これもいいや!
さらに得点を伸ばしたいなら、予備校の単科講座がおすすめです!
- もっと得点を伸ばしたい!
- 全体的にレベルアップしたい!
- でもなるべくお金はかけたくない・・
こんな方には予備校の単科講座がおすすめです。
単科講座なら自分が受けたい科目だけ予備校の講義を受けることができます。
予備校通学に比べて格安で受講できる上に、通信講座だと時間と場所も選びません。
詳しくは下記の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。